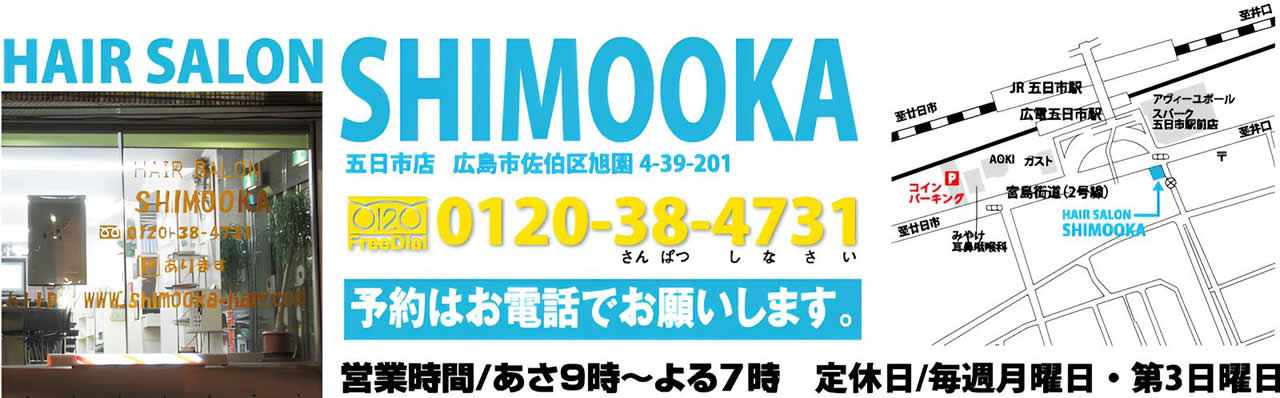- トップページ
- お役立ちコラム
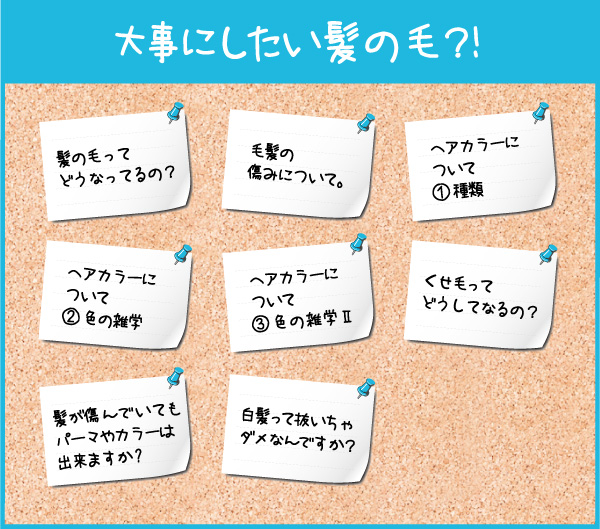
髪の毛ってどうなってるの?
髪の毛について少し知ってみましょう。 髪の毛って何で出来ているか知っていますか?そう、タンパク質です。 皮膚も爪も主にタンパク質で出来ています。タンパク質を分解してゆくと小さなアミノ酸になります。アミノ酸が2~100個くらい重合(手をつないだ感じの状態) してPPT(ポリペプチド)となります。
たくさんのアミノ酸(100個以上)が集まって重合し タンパク質となるのです。20種のアミノ酸が複雑に重合して体の組織を形成しており、 髪の毛や爪などは「ケラチンタンパク質」という硬いタンパク質で形成されており、皮膚表面の角質層も 「ケラチンタンパク質」、皮膚の中は「コラーゲンタンパク質」 という柔らかいタンパク質」で形成されています。
ちなみに、人の体は10万種類のタンパク質で形成されているそうです。髪の毛は、約10万本あり、太さは50~100ミクロン、 pH4.5~pH5.5、水分量11~13%くらいです。
毛髪の傷みについて
「髪へのダメージ」とか「髪の傷み」とか良く言われますね、 どんな状態を言うのか、またはどういうことで起こるのか。 髪が傷むとは「表面の傷み」と「内部に及ぶ傷み」とに分けられます。表面の傷みとは「キューティクルの損傷」で、 ブラッシングやドライヤーなどの物理的損傷でキューティクルが剥がれたり変形したりして髪本来の「ツヤ」「まとまり」 「手触り」が悪化します。「内部に及ぶ傷み」とは「表面の傷み」 からの進行や、紫外線、パーマ剤やカラー剤に含まれたアルカリなどの影響により栄養分(間充物質)が流れ出したりタンパク質の変質や分解・損失が起こり、保湿力を失ったり、進行すると髪本来の強さが無くなることにより「切れ毛」「ちじれ毛」「ポーラス(多孔質)毛」などを引き起こします。
「表面の傷み」は日常生活でのブラッシングやシャンプー、ドライヤーの熱、プールや海で泳いだ後などにも起こりうるので、過度または力の入ったブラッシングやシャンプー、 ドライヤーのかけ過ぎや至近距離での使用を注意し、 泳いだ後は優しいシャンプーを行い、 トリートメントまたはコンディショナーで弱酸性状態に (バッファー効果によりpH変化の低減)お手入れされることで 防ぐことができます。
「内部に及ぶ傷み」は、「表面の傷み」での対処はもちろんのこと、 紫外線防止の対策(帽子の着用やUV効果のトリートメントや 整髪料)をすること、パーマ剤やカラー剤の場合はスタイリストが 過度なアルカリ使用やマッチングに気を付け最良の施術を行い、お客様はスタイリストのアドバイス(トリートメントやお手入れ方法などのホームケア)を聞いていただくことで防ぐことができます。
ヘアカラーについて ①種類
ヘアカラーと呼ばれるものはたくさんありますよね?
サロンで染めてもらうヘアカラー、ドラッグストアなどで
売られているホームカラー、たくさんのメーカーや種類が
出回っています。
お客様から「たくさんありすぎて分かんない」と言う声を
良く聞きます。ごもっともだと思います。
そこで、大まかにご説明しようと思います。
ヘアカラー(染毛剤)は大別すると
「一時染毛剤」、「半永久染毛剤」、「永久染毛剤」と
3種類に分けることができます。読んで字のごとし・・・「一時染毛剤」とは染めた後、シャンプーすることで落とせる、つまり「一時的」に使われ表面に付くだけのものです。カラースプレーやブラシで塗るもの、マスカラタイプもあります。
主原料は顔料(水、油、アルコールなどに溶けない有色不透明の粉末で、粉末分散のままで物を着色する色料)。
薬事法の分類では「化粧品」になります。薬事法での「化粧品」とは・・・「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。
「化粧品」は2001年4月、「全成分の表示」が義務づけとなり、どのような成分が含まれているのかが明確に
わかるようになりました。「半永久染毛剤」とは、表面とキューティクル(毛表皮)とCMC(細胞膜複合体)を含むキューティクル領域に染まり着くもの。髪の毛自体を脱色したり、明度を上げる(明るくする)ことはできません。
ヘアマニキュアやカラーリンスなどがある。主原料は酸性染料または塩基性染料。薬事法の分類では「化粧品」になります。「永久染毛剤」とは・・・髪の中まで染めるもので、ブリーチで明るく出来るものと出来ないものがあります。
酸化染毛剤(アルカリカラー・医薬部外品)は明度を上げることもできます。(市販品の1剤・2剤を混ぜて使うものはこれにあたります)。
非酸化染毛剤(医薬部外品)や植物染料(ヘナなど・化粧品)は明るくすることはできません。主原料は酸化染料、アルカリ剤または植物系原料など。薬事法の分類では「医薬部外品」となるものと「化粧品」のものがあります。
薬事法での「医薬部外品」とは・・・「人体に対する作用が緩和である、疾病の診断、治療または予防に使用せず、身体の構造、機能に影響を及ぼすような使用目的を合わせ持たないもの」と定義されています。
「医薬部外品」には、全成分表示の義務付けがなく、「指定表示成分表示」だけで良いので、指定表示成分以外に
どのようなものが入っているかわかりにくく、「肌にとってよくないもの」が含まれていても分からないことがあります。
ヘアカラーについて ②色の雑学
ヘアカラーをもっと知っていただくため、雑学を少し・・・。
色ってどうして見えるのでしょう?
人の目が色として認識するためには条件が必要です。
①光源(太陽や蛍光灯など)
②反射物(壁や車、紙など)
③視覚(網膜にある細胞)
以上の三つが揃うことで「色」としての認識ができるのです。
一つでも欠けると「見えない」ということです。
光が物体に当たって反射、それを目の網膜でとらえて「〇〇色」と 認識します。
たとえば「赤い車」という表現は少し違ってきます。
「光の中の赤い光だけを反射する塗料に塗られた車」と言った方が正しいですね。
色は光です、光は波長、つまり電波ですね。太陽光はさまざまな波長の光を含んでいます。その中で人の目に認識できる波長は400~700ナノメーターです。
虹やプリズムで見える「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」などが 認識できる波長(可視光線)です。400ナノメーター辺りが紫、700ナノメーター辺りが赤です。400より波長が短く(周波数、高)が紫外線(UV)、700より波長が長く(周波数、低)が赤外線(IR)と呼ばれ、いずれも人の目には認識できません。 (不可視光線、つまり見えません)
人の目が識別できる色の数は諸説ありますが、1677万色以上とも言われています。パッと見ただけでも2万色以上瞬時に識別できるそうです、 人間ってすごいんです。
ヘアカラーについて ③色の雑学Ⅱ
色の表現の仕方って難しいと思いませんか?
「赤い」といってもどんな赤なのか・・
「真っ赤な赤」「トマトの様な赤」「ポストの赤」 「燃えるような赤」など、いろんな「赤」があり人それぞれに表現の仕方って違いますよね。
世界の中でも特に日本人は繊細な表現をする民族だそうです。
それは、日本語の中で色を表す言葉の多いことでもわかります。
一般的な「赤、青、黄色、緑、橙、紫、藍、空、黄土、桃、 黄緑、焦げ茶、朱、肌、紺、鼠、深緑、群青、金、銀、灰、 黒、白」などの他に「桜、草、瑠璃、萌黄、卵、薄墨、小豆、 山吹、茜、若草、漆黒、抹茶、檸檬、栗、鶯、象牙、エンジ、 褐色、生成、小麦、琥珀、真紅、紅、乳白、若葉、薔薇、 牡丹、黄金、飴」とかありますし、 「苺、狐、純白、曙、松葉、柿、菜の花、亜麻、江戸紫、 駱駝(らくだ)、柳、珊瑚、苔、煉瓦、蒲公英(たんぽぽ)、 蜜柑、梔子(くちなし)、白金、千草、露草、薄紫(浅紫)、 葡萄、胡桃、ウコン、朽葉、」
もっともっとたくさんの表現があります。
聞きなれないものでは、「青磁(せいじ)、鳥の子、 鉛丹(えんたん)、石板(せきばん)、黄櫨色(はじいろ)山鳩、赤丹(あかに)、青丹(あおに)、練(ねり)、唐茶、鶸(ひわ)、弁柄、黄橡(きつるばみ)、藍鼠(あいねず)、緑青(ろくしょう)、常磐緑(ときわみどり)、浅葱(あさぎ)、木蘭(もくらん)、麹塵(きくじん)、安石榴(ざくろ)、薄浅葱、金春(こんぱる)、鉄紺、白緑(びゃくろく)、柑子(こうじ)、納戸、花田、勿忘草(わすれなぐさ)、青摺(あおずり)、菖蒲(しょうぶ)、杜若(かきつばた)、海松(みる)」
聞いただけでは何色かわかりませんね・・まだまだありますがこの辺にしておきましょう。
日本ではこれに「英語」などの外来語(ネイビーブルー、 ターコイズブルー、カーキ、ワインレッド、セピア、オリーブ、 モスグリーン、サーモンピンク、スカーレットなど)を使って 色を表現しますので数えきれないくらいあるでしょうね。
日本の色の呼び方にはその物の色をあらわすだけでなく、季節や温度、質感、感情まで表現されているものも
たくさんありますね。
くせ毛ってどうしてなるの?
毛髪についての質問の中に「くせ毛について」良く聞かれます。
毛髪がうねったりねじれたりする「くせ毛」と立ち上がったり一方方向に流れたりする「生えぐせ」があります。
「くせ毛」は毛根が曲がっていたり、いびつな形をしていて伸びてゆく時曲がったまま伸びたり、断面が楕円形だったりすることでねじれて伸びてゆきます。しかし、人毛はどなたの物も断面が丸い毛髪は1割程度で9割は楕円形だったりいびつだったりしていますのでくせの無い毛髪の方が少ないのです。
それと、毛髪内部のタンパク質の配列にも原因があります。毛髪の内側に「コルテックス(Cortex)」という部分があります。ここに吸水性タンパク質と撥水性タンパク質があり、バランス良く配列していれば直毛に近くなります。
しかしバランスが偏っていると吸水性タンパク質は水分を含みやすく含むと伸びます。撥水性タンパク質は水分をはじきますから伸びにくいので伸び方に差が生じます。
これが曲がったりうねったりの原因になります。湿度の高い「梅雨時期」にくせ毛が強く表れるのはそのためです。
くせ毛の強い弱いは以上の2点がどのように出来ているかで差が出来るのです。
生えぐせは、毛髪が地肌に対してどの程度の角度で生えているかで決まります。毛穴が直角に近ければ立ちやすい毛髪になりますし、毛穴が前に向いていれば前に向かっての生えぐせと言えますね。
毛髪を含め体毛のほとんどは直角ではなく角度がついて生えています。頭には毛渦(ギリとかウズと呼ぶ)があり、右巻とか左巻とか言いますよね。
もうひとつは「立毛筋(起毛筋)」で支えられて生えた毛の角度を保ってもいます。寒い時など腕の毛が立ったりする「鳥肌」は立毛筋が収縮し毛穴が盛り上がることで起きます。
頭髪の物はそこまで収縮しませんが、毛髪をある程度の角度で維持しています。加齢が進むと弱ってきますので、髪の角度が緩やかになり「ねかせ易く」なります。トップのボリュームが無くなりペチャッとなるのもこれが一因です。
髪が傷んでいてもパーマやカラーは出来ますか?
髪は出来るだけ傷めたくないものです。しかし、以前もお話ししましたが、シャンプーや紫外線、水に濡れるだけでも痛むことがあります。
お客様の毛髪状態を良く観察し、パーマやカラーが出来るのかどうか、出来るならどんな薬液をどのように使うのか、ケアはどうするかなどを判断するのも「プロの仕事」です。
傷みのレベルや仕上げスタイルなどによっては「施術をしない」選択をする場合もあります。
髪の状態は日々変わっていると言っても過言ではないのです。どんな場合でも、お客様に解りやすくご説明し、納得いただいた上で決定いたします。
お客様では判断しずらい「今の毛髪状態」は、カウンセリングで診断、お知らせする事も出来ます。
カウンセリングは無料です、お気軽に相談しに来てくださいね。
白髪って抜いちゃダメなんですか?
はい、抜いちゃダメです!
白髪の出始めは1本~数本ですから「無かった事にしたい」 お気持ちはよく分かります。
しかし、白髪は「健康な髪」なのです。健康な髪の毛を無理に抜いてしまうと、毛根や毛母細胞を傷付け、正常な細胞分裂が出来なくなる恐れもあります。弊害としては「変形毛(くせ毛、ビビり毛等)が生える」 「毛髪自体が生えなくなる」などです。
毛髪は毛根の下、毛母細胞で作られます。毛細血管から毛乳頭へ養分が貯められ、そこから養分を毛母細胞に取り込み、細胞分裂を繰り返して毛髪を作り出しています。その毛母細胞のすぐそばに色素細胞(メラノサイト)がありメラニン色素を作り出し、毛髪に取り込むことで毛色(黒髪、赤毛等)が決まると言われています。
すなわち、毛母細胞から生まれたばかりの毛髪には色は無く白髪なのです。色素細胞が弱ったり無くなってしまうと、メラニン色素を取り込むことや作ることが出来なくなり白髪になるのです。
ですから、白髪はメラニン色素が無いだけで「健康な毛髪」なのです。最近になって、髪の毛が生え換わるときに色素細胞も一緒に失われることもあることが分かってきたようですが、毛根の状態が良ければ新しく色素細胞も再構築され、メラニン色素を作り、元の色髪に戻ることも分かってきました。
近い将来、色素細胞ケアの技術も開発されるかもしれません。
出来る白髪対策は、数本で抜きたくなったら「ハサミで地肌近くを切る」方が毛根を傷めません。もっと増えてくると「白髪ぼかし」がお勧めです、完全に染めてしまわずに「グレイに染める」と目立ちにくくなります。
傷みも気になる場合は「酸性カラー」でぼかして染めるのがお勧めです、アルカリを使わないので傷みはありません。一部分に出ている場合はホイルワークやウィービング等で対処出来ます。そのほかにも数種類の方法がありますのでお気軽にご相談くださいませ。
御自宅でホームカラーやマニキュアをされる場合もご相談いただければ、より良い使用方法などアドバイス
いたしますので気軽に聞いてくださいね。